科学分析
<古代瓦胎土分析−X線回折試験および化学分析> 井上 巖((株)第四紀 地質研究所)
本遺跡出土資料も含め、主として矢作川流域の古代寺院関連遺跡から出土した瓦の比較研究を行うために、胎土分析を行うことにした。合計253点を選び出し、胎土分析を株式会社第四紀地質研究所に依頼した。分析資料サンプルは以下の通りである。
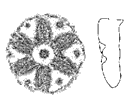 資料1(北野廃寺跡)
資料1(北野廃寺跡)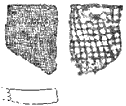
資料60(牛寺廃寺跡)
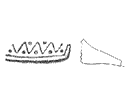
資料133(市道遺跡)
- 北野廃寺跡(旧碧海郡)…分析資料1〜18
- 真福寺東谷遺跡(旧額田郡)…分析資料19〜28
- 丸山廃寺跡(旧額田郡)…分析資料29〜34
- 伊保白鳳寺跡(旧賀茂郡)…分析資料35〜54
- 牛寺廃寺跡(旧賀茂郡)…分析資料55〜64
- 雨堀瓦窯跡(旧碧海郡)…分析資料71〜76
- 志貴野遺跡(旧碧海郡)…分析資料77〜88
- 北迫瓦窯跡(旧幡豆郡)…分析資料89〜105
- 寺部堂前遺跡(旧幡豆郡)…分析資料106〜116
- 鳥羽神宮寺跡(旧幡豆郡)…分析資料117〜127
- 市道遺跡(旧渥美郡)…分析資料128〜139
- 弥勒寺跡(旧宝飫郡)…分析資料140〜147
- 別郷廃寺跡(旧碧海郡)…分析資料148〜156
- 大久根遺跡(旧碧海郡)…分析資料157〜162
- 寺領廃寺跡(旧碧海郡)…分析資料163〜182
- 神明瓦窯跡(旧碧海郡)…分析資料184〜197
- 舞木廃寺跡(旧賀茂郡)…分析資料198〜204
- 勧学院文護寺跡(旧賀茂郡)…分析資料205〜207
- 下り松瓦窯跡(旧賀茂郡)…分析資料208〜219
- 医王寺廃寺跡(旧宝飫郡)…分析資料220〜223
- 山ノ入遺跡(旧宝飫郡)…分析資料224〜229
- 三河国府跡(旧宝飫郡)…分析資料230〜239
- 古新田遺跡(旧碧海郡)…分析資料240〜259
65〜70欠番
1)「IIIタイプ:Qt:中・Pl−低」丸瓦は北野廃寺跡、丸山廃寺跡、志貴野遺跡、寺部堂前遺跡、三河国府跡、大久根遺跡、雨堀瓦窯跡とともに古新田遺跡の瓦が共存する。平瓦は北野廃寺跡、丸山廃寺跡、牛寺廃寺跡、伊保白鳳寺跡、寺領廃寺跡、医王寺跡、鳥羽神宮寺跡、神明瓦窯跡とともに古新田遺跡の瓦が共存する。
2)「IIIタイプ:Qt:小・Pl−低」丸瓦は伊保白鳳寺跡、鳥羽神宮寺跡、寺領廃寺跡、志貴野遺跡、北迫瓦窯跡の瓦が共存する。平瓦は伊保白鳳寺跡、別郷廃寺跡、志貴野遺跡、鳥羽神宮寺跡、勧学院文護寺跡、北迫瓦窯跡等とともに古新田遺跡の瓦が共存する。
3)「IVタイプ:Qt:中・Pl−低」丸瓦は神明瓦窯跡、弥勒寺跡、舞木廃寺跡、別郷廃寺跡、牛寺廃寺跡、とともに市道遺跡と山ノ入遺跡の瓦類が共存する。平瓦は北野廃寺跡、牛寺廃寺跡、寺領廃寺跡、舞木廃寺跡とともに神明瓦窯跡、北迫窯跡、雨堀瓦窯跡の瓦が共存する。
4)「Iタイプ:Qt:小・Pl−低」丸瓦は北迫窯跡の瓦が集中し、三河国府跡の瓦が混在する。平瓦は北迫瓦窯跡の瓦が集中し、三河国府跡の瓦とともに寺部堂前遺跡、志貴野遺跡、古新田遺跡の瓦が共存する。
5)「IIIタイプ:Qt:小・Pl−高」丸瓦は寺領廃寺跡、寺部堂前遺跡、伊保白鳳寺跡、別郷廃寺跡の瓦とともに古新田遺跡の瓦が共存する。平瓦は伊保白鳳寺跡、寺領廃寺跡、寺部堂前遺跡、志貴野遺跡の瓦とともに、雨堀瓦窯跡、北迫瓦窯跡、古新田遺跡の瓦が共存する。
6)「IVタイプ:Qt:小・Pl−低」丸瓦は北野廃寺跡、真福寺東谷遺跡、伊保白鳳寺跡、別郷廃寺跡、大久根遺跡、舞木廃寺跡とともに神明瓦窯跡と三河国府跡の瓦が共存する。平瓦は北野廃寺跡、舞木廃寺跡の瓦が共存する。
7)「IVタイプ:Qt:中・Pl−高」丸瓦は牛寺廃寺跡、真福寺東谷遺跡、とともに神明瓦窯跡と山ノ入遺跡の瓦が共存する。平瓦は真福寺東谷遺跡、寺領廃寺跡の瓦とともに神明瓦窯跡が共存する。
※) Pl−高とは焼成ランクが低い瓦、Pl−低とは焼成ランクが高い瓦で焼成環境が異なることを意味する。Qt−小とは混入される砂の量が少ない、Qt−大とは混入される砂の量が多いことを意味
する。
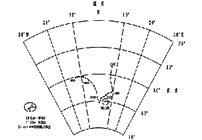
焼土坑焼土の残留磁化方向と広岡・藤沢(1988)の考古学磁気永年変化曲線の一部
 広岡・藤沢(1988)による東海地方の考古学磁気永年変化曲線(太線)
広岡・藤沢(1988)による東海地方の考古学磁気永年変化曲線(太線)焼土坑の焼成年代推定値